瑕疵(かし)とはキズを意味する言葉で、
2020年3月末までの民法には、瑕疵担保責任という制度があり、
不動産の売買においては瑕疵という言葉がよく使われています。
2020年4月1日から改正民法(債権法)が施行され、
契約不適合責任 に変わりました。
不動産業界の方は、
むやみやたらに、「瑕疵(かし)」という単語を
使う印象があります(私の周りだけ?)
建築物の契約不適合(瑕疵担保)責任とは
もともと「通常あるべき品質・性能を有しないこと」を意味するので、
建物の場合、土地や建物にある何らかの不具合や欠陥のことをいいます。
引渡し後の土地や建物に瑕疵が見つかった場合、
買主は、売主に対して補修や賠償請求ができる権利のことです。
請求できる期間があるのですが、改正後は、買主に有利になっています。
瑕疵の分類は、法的に以下のように分類されるようです。
①「客観的瑕疵」、「主観的瑕疵」の2つ
②「物理的瑕疵」、「心理的瑕疵」、「環境的瑕疵」、「法律的瑕疵」の4つ
客観的瑕疵とは
通常有すべき品質・性能を欠いていること
もともとの瑕疵の意味と一緒ですね。
標準的な技術水準に合致しているかどうか、法令遵守しているか
主観的瑕疵とは
当事者が契約で定めた内容の適合性が問題となりますので、
設計図書、契約図書等のとおりの建築物となっているかどうか
物理的瑕疵とは
不動産の物理的な欠陥のこと
例えば、
建物の床の傾き、雨漏り、シロアリによる床下の腐食など
土地の土壌汚染や地中障害物、擁壁の破損など
欠陥(瑕疵)の判断は
その欠陥が、
・現象なのか
・原因が特定できているのか
ここが、重要です。
欠陥現象を羅列していても、請求としては不足ですので、
欠陥原因が特定できれば、請求が可能になります。
例えば、
壁にひび割れがある→現象
⇒雨漏りが原因と特定できた→請求可能
⇒他の壁にも、ひび割れが見つかった→現象
要するに、
事象のみを羅列していても、請求としては不足
(ひび割れが散見される とか)
欠陥原因が特定でき、
それが「通常あるべき品質・性能を有しない」、
「設計図書、契約図書等のとおりではない」
といえるかどうか。
「雨漏りが原因だった」と、わからない状態で請求しても
「壁のコンクリート(木材など)、またその仕上げは、設計図書通りですよ」
と回答があるだけ。
瑕疵という表現が残っている工事請負契約約款
公共工事標準請負契約約款
民間工事標準請負契約約款
下請標準請負契約約款
どちらにも、「瑕疵担保」の規定があります。
参考⇒国交省の資料に飛ぶ 6ページ以降
・・・
民法から消えても、建築関係では、「瑕疵」が残っている
・・・
難しい
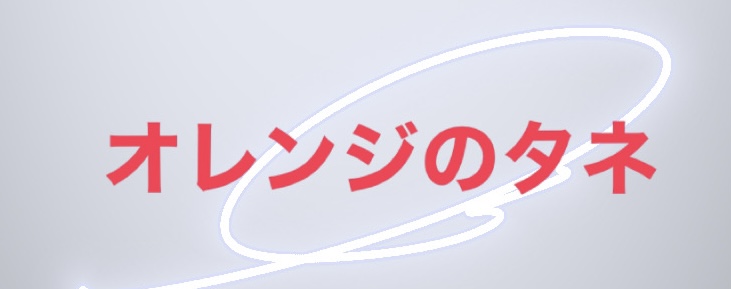


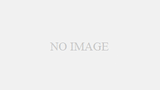
コメント